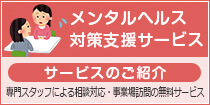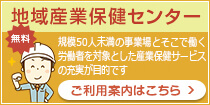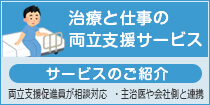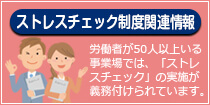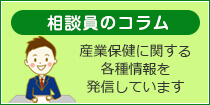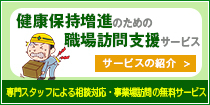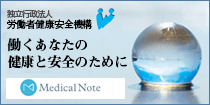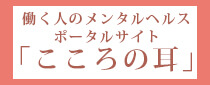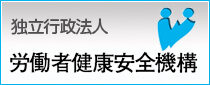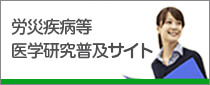産業保健コラム
辰巳 朋子
所属:平安女学院大学非常勤講師
専門分野:臨床心理学・産業カウンセリング・ストレスマネジメント
改めて、心理的安全性を
2025年6月2日
この原稿を読んでいただく頃、雨は降っているでしょうか。四季が二季となり、紛争や災害、政治・社会状況等のニュースも社会の落ち着かなさを伝える昨今、この国の小中高生の自殺が、前年から16人増加で529人と報告されました。統計を取り始めた1980年以降最多とのこと。対応策も色々と行われて、保護者も教師も様々の支援者も、真面目に誠実に取組んでいるはずなのに、私達大人は何か、どこで何を…。
心理相談員として、今月は改めて「心理的安全性」をお伝えします。この言葉は、多国籍企業Googleにおいて「効果的なチームは、どのようなチームか」という調査の結果見出されました。問題だったのは、どのようなメンバーかではなくて「チームがどのように協力しているか」という側面であり、その中で特に重要だった特徴が、「心理的安全性」と翻訳されました。この結果は注目を集め、いかにして心理的安全性を作るかの企業研修も盛んです。つまり、今を生きる私達が協力し合う場面においては、人間関係のリスクを下げる配慮が最大限に重要だということがわかったのです。長年心理相談を受けてきますと、チームだけでなくて、家庭や学校、生活場面でも同じような人間関係の危機が潜んでいると思われるのです。
例えばこんな例はどうでしょうか。チームスポーツでよく見られる一致団結の空気は、異議を唱えにくい雰囲気を高めますが、皆が同じ方向を向いて「!」となっている時に、反対意見が表明されたら、それを私達は聞くことができるでしょうか。あるいは、問題やリスクに自分が気づいた時に、ためらわずに声をあげられるでしょうか。意見の対立が起こることでより良いアイデアが生まれるのだとか、前例や実績にこだわりすぎない、等というチャレンジ精神を、私たちは集団や組織の中で発揮できているでしょうか。
建設的なフィードバックを、ハラスメントと明確に区別して、次世代に伝えるコミュニケーションを願っています。
辰巳 朋子