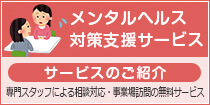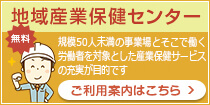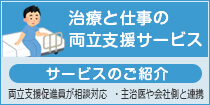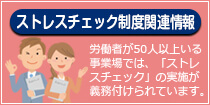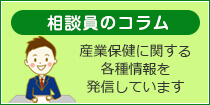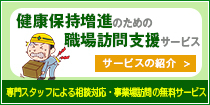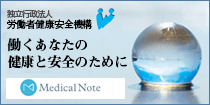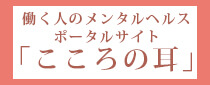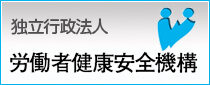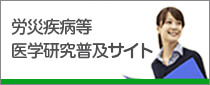産業保健コラム
花谷 和雄
所属:花谷社会保険労務士事務所
専門分野:特定社会保険労務士・公認心理師・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント
お寺のお手伝いから見えるもの
2025年9月1日
皆さん、お墓参りに行ってますか?
私が縁あってお寺の行事を手伝いだしてから60年以上になります。お寺に嫁いだ叔母からの頼みでスタートしたのですがお寺というものが意外と性に合っていたのか気づけば半世紀を優に超えてしまいました。勿論、毎日ではなく、大きな法要の都度手伝いに行くのですが法要の準備・後片付け、本堂や周囲の掃除から始まり先々代の住職の時は、小僧のように住職の棚経の運転手などをして来ました。当時の住職にも可愛がってもらいお寺全体の雰囲気や住職の立ち振る舞いや雑談を通じて様々な体験をすることが出来私の人生に大きな影響を受けました。
先日も法要の受付をしたのですが昔は、お布施を必ず金封に入れて納められました。ところが最近は、原則むき出しです。先日の法要でお参りされる檀家の方は、200人ほどですが金封に入れてこられる檀家は数人程度になりました。中には、財布から直接出される方もおられます。細かいことですがこれまでの習慣が変わっていくことを実感していますし、この他にも時代とともに変化した習慣は多くあると思います。
それから感じるのは、高齢化です。以前は、小さい子どもを連れて参詣される檀家が多くありましたが最近お子さん連れは非常に少なくなりました。高齢化に伴い参詣される人数も減ってきています。お寺にお参りするという習慣が次世代に上手く引き継がれていないと感じています。
私がお手伝いを始めてから今の住職が3代目なのですが現在この住職は、郡部の3件のお寺の住職を兼任されています。郡部では、過疎化そして高齢化が顕著で住職が常駐出来る状態にはないそうです。そして、この状態は、日本全国に広がっています。
これは単にお寺(仏教)のみの問題ではありません。都市部以外では、お寺は、コミュニテイの大きな役割を担ってきたのでお寺が機能しなくなると地域の活力がそがれていくのです。住職もそれを肌で感じておられるようです。最近は、お寺の存在意義が小さくなっているようです。しかし、地域の大小のお寺の存在が地域のまとまりと文化の継承を担って来ました。私は、お寺の存続は、日本文化を守り我々の精神性を保持出来る大きな要素と考えています。大袈裟かも知れませんがお寺の減少は、日本文化の衰退と直結しますので現状を憂慮しています。
皆様もお墓参りをすることによって日本の文化・習慣を見直すきっかけにされては如何でしょう。
花谷 和雄