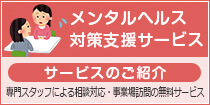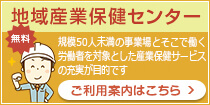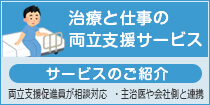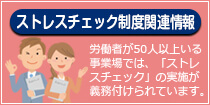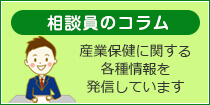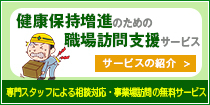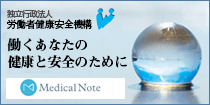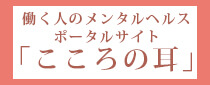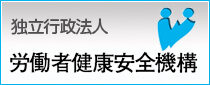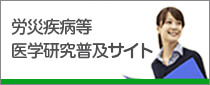産業保健コラム
西村 和記
所属:SRオフィス西村
専門分野:特定社会保険労務士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント
育児支援と治療と仕事の両立支援
2025年10月1日
令和7年4月より産後パパ育休がより充実し、男性が配偶者の産後休業期間中に14日以上、育休を取得すると育児休業給付金の67%に13%が加算され計80%となり、社会保険料の免除と合わせると手取り収入が減少しないとされます。またこの13%は配偶者も就労して雇用保険に加入し育児休業給付を受ければ、同様に加算されます。
これら充実の影響もあるためか、4月以降の男性育休が急増した、と感じておられる人事労務担当者は多いのではないかと思います。当初は、業務の代替要員の確保にハラハラされていらっしゃった人事担当者や各リーダーも施行後半年が経過し、ある程度落ち着かれたかなと希望的に思っています。
10月から、もう準備はすでにされていると思いますが、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置、それら措置の個別の周知・意向確認、そして両立支援として、妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取、これらは「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいのは言うまでもありません。その意向についての配慮の義務が始まります。これらもすでに実施されている企業様も多いかと思いますが、改めてご確認下さい。
両立支援では、上記のように仕事と育児の両立支援とは別に、治療と仕事の両立支援について厚生労働省は「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を当初は平成28年2月に作成し、その後データも充実され、現在は令和6年3月版が作成され、取り組みが進められています。
ガンをはじめ脳卒中、心疾患などかつて「不治の病」とされていた疾病も「長く付き合う病気」に変化しつつあり、病気にかかってもすぐに退職する必要に必ずしも当たらなくなっています。ただ本人が職場に迷惑をかけてしまうなどと自ら思い込んだり、仕事を優先しすぎて治療を適切に受けずに病気を悪化させてしまう事例も耳にします。
能力や意欲のある人材を「病気だから」と単純に敬遠せずに取り組むことは健康経営やワークライフバランス、ダイバーシティ経営の観点からも望まれます。わかりやすい法的根拠としては労働施策総合推進法の第6条で、労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活と調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備について努力義務とされています。
この治療と仕事の両立支援につきまして京都産業保健総合支援センターで企業様を対象に支援活動をしています。個別訪問支援も可能ですので、どうぞご利用下さい。
京都産業保健総合支援センター 治療と仕事の両立支援サービス
https://www.kyotos.johas.go.jp/ryoritsu
西村 和記