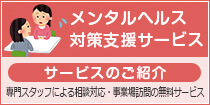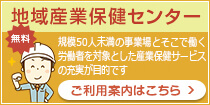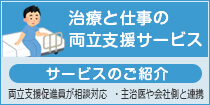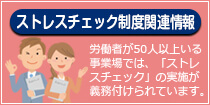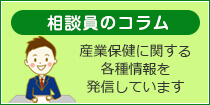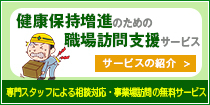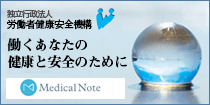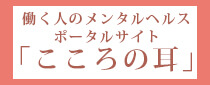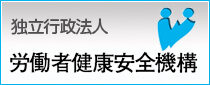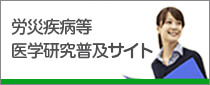産業保健コラム
松井 大輔
所属:京都府歯科医師会 公衆衛生委員会
専門分野:産業歯科
歯科特殊健康診断を受けておられますか?
2025年10月1日
2023年4月より、労働安全衛生法に基づく新たな化学物質規制が施行され、リスクアセスメントを基本とした管理への移行が始まりました。さらに2024年4月からは、化学物質管理者および保護具着用管理者の選任が義務化されています。
化学物質と歯科との関連では、労働安全衛生法第66条第3項に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して、歯科特殊健康診断(化学物質による歯牙酸蝕症その他の疾患等の検査)を6か月以内ごとに1回実施することが必要です。対象となる化学物質は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんなど、歯やその支持組織に有害なものです。また、歯科特殊健康診断については、令和4年10月1日より、労働者数に関わらず(それ以前は50人以上の事業所のみ対象)、所轄労働基準監督署長への結果報告が義務化されました。さらに令和7年1月1日からは、結果報告の電子申請が義務化されています。
厚生労働省が令和2年に実施した調査によると、酸などを取り扱う事業所のうち、歯科特殊健康診断を実施している割合は全体で31.5%でした。50人以上の事業所では55.6%が実施している一方、50人未満の事業所では22.5%と低い水準でした。
私自身も歯科特殊健康診断を行っていますが、報告義務化の影響もあり、小規模事業所での実施が増えている一方で、大規模事業所でも未実施の例を目にします。法定健診ではありますが、私が担当する事業所では、健診をきっかけに口腔への健康意識が高まり、一般歯科健診を積極的に受診する従業員が増え、健康経営にもつながっていると実感しています。実施されない理由としては費用面のほか、「どこに依頼すればよいかわからない」という声も多く聞かれます。事業所で歯科特殊健康診断が議題に上がった際には、京都産業保健総合支援センターへご相談いただけますと幸いです。
松井 大輔