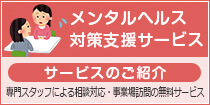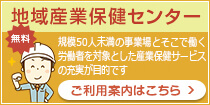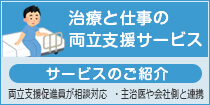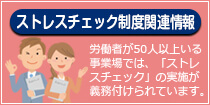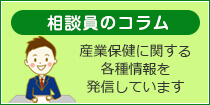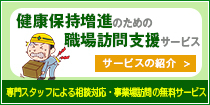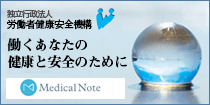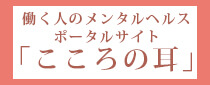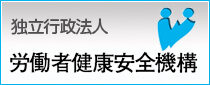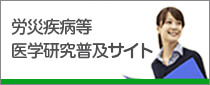バックナンバー
**************************************************
京都産業保健総合支援センター メールマガジン302号 2025/8/4
発行:京都産業保健総合支援センター 所長 松井 道宣
ホームページ:https://www.kyotos.johas.go.jp
**************************************************
当センター主催 産業医研修会ついて
8月~9月開催研修会 受付中
2025年4月以降実施の日医認定産業医研修会受講の単位管理等は、
日本医師会会員情報システム【MAMIS】に移行されました。
【MAMIS】マイページ登録を完了いただくようお願いいたします。
非会員の方も登録が必要です。
*日本医師会産業医部会連絡協議会
https://www.sangyo-doctors.gr.jp/Notice
・MAMIS稼働に当たっての留意点
・4月1日以降開催の認定研修会単位の閲覧について
・コロナ特例の終了について(2028年3月末)
*セミナー・研修の詳細・お申込み
https://www.kyotos.johas.go.jp/training-new
**************************************************
————————————————————————————————–
◇ 京都産業保健総合支援センター ホームページ情報 ◇
1)日本医師会 MAMIS稼働にあたっての留意点
2)中央災害防止協会「第84回全国安全衛生大会in大阪・近畿」のご案内
3)令和7年度 団体経由産業保健活動推進助成金について
————————————————————————————————–
**************************************************
◇転倒しない身体作り-「ロコモ」「フレイル」「サルコペニア」?-◇
産業保健相談員(産業医学) 高橋 真
皆さんは最近ご自身が転倒されたり、転倒された方のことを聞かれたりしたことはないでしょうか?不可抗力で起こる場合もあるでしょうが、少なくとも自身の筋力やバランス力不足の為に転倒するのは避けたいと思われませんか?
私達は年を取ると、歩くのが遅くなり、歩ける距離も短くなる、食欲が落ちる、成人病やがんのリスクが高くなる、トイレが近くなる、目や耳が不自由になる、物忘れが酷くなる、など様々の不具合が生じてきます。中にはそれらの悪化により、介護を要する状態になられる方もおられます。実は要介護になられる原因の第4位が「転倒」なのです(1位認知、2位脳卒中、3位衰弱)。
肥満・高血圧・高血糖などに関連した「メタボ」は既にご存知の方が多いことと思われます。では「フレイル」や「ロコモ」という単語はご存知でしょうか?
「フレイル」を直訳すると「虚弱」という意味で、『健常・健康』と『身体機能障害・要介護』の間の状態を指します。つまり少し進めば要介護になる一歩手前の状態ということです。
「フレイル」は 1.身体的フレイル(筋力低下・低栄養など) 2.精神・心理的フレイル(鬱・物忘れ・意欲低下など) 3.社会的フレイル(閉じこもり・交流無しなど) という3つの要素に分けられるのですが、その中でも身体的、特に骨・関節・筋肉など運動器機能の低下したものを「ロコモ(ロコモティブシンドローム=運動器症候群)」と呼び、更に筋力・筋肉量低下に特化したものを「サルコペニア=筋肉減少症」と呼んでいます。
「フレイル」「ロコモ」「サルコペニア」にはそれぞれ判定根拠となるチェックリストがあり、「フレイル」には15項目の基本チェックリストやその簡易版(5項目)が、「サルコペニア」は握力・椅子からの立ち上がり時間(5回)の2項目が判定根拠とされています。
また「ロコモ」では7つの動作が可能かのロコチェック、ロコモ度テスト(椅子からの立ち上がり・2ステップテスト・チェックリスト25項目)等により、ロコモ度1・2・3の3群に分け、それぞれに推奨される指導が日本整形外科学会・日本臨床整形外科学会の監修の下に行われています。「ロコモ度1」の群には「サルコペニア・フレイル」の方がほぼ完全に含まれますので、ロコモ度の進行予防で「サルコペニア・フレイル」の予防にもなるのです。
詳細はパソコンの検索やYou Tube などでご覧になれますが、「ロコモ」を予防する為の体操(ロコトレ)として、スクワット(膝を曲げる・伸ばす3秒かけて、5~6回1セット1日3回)、片足立ち1分(1分間1セット1日3回)の2つの体操が推奨されています。単純で面白くもない体操なので、なかなか長続きしないかも知れません。ただ「フレイル」と判定された方の6人に1人は2年後には要介護状態になられているというデータもありますので、要介護状態にならない為にも、ご自身を「転倒」から救う為にも是非ロコトレを試してみて下さい。
**************************************************
◇ 座りっぱなしに注意 ◇
メンタルヘルス対策・両立支援促進員 小澤 裕美子
先日ニュースの中で「座りっぱなしを防ごう」という特集があった。長時間座り続けることの健康リスク、職場での対策例として、仕事をするときに昇降式デスクを利用して立って仕事をする、座って行う会議の中にストレッチをする時間を設けて身体を動かす、という方法が紹介されていた。ネットでも「座りっぱなし」で検索するとたくさんの情報がある。
厚生労働省が10年ぶりに改訂した「身体活動・運動ガイド2023」(以下「ガイド」と呼ぶ)の中で、座位行動(座りっぱなし)という概念が初めて取り入れられた。ガイドでは座位時間が長いほど、死亡リスクが増加することが明らかなこと、1日60分以上の中強度以上の身体活動によって、座位行動による死亡リスクの低下が期待できることや長時間の座位行動をできる限り頻繁に(例えば、30分ごとに)中断(ブレイク)することが、食後血糖値や中性脂肪、インスリン抵抗性などの心血管代謝疾患のリスク低下に重要である等の報告があると書かれている。このガイドの一般向け周知用リーフレットには「座りっぱなし」という言葉が何度も出てくる。
話はそれてしまうが、「座りっぱなし」という言葉を最初に見たとき、私は違和感があった。長時間座り続ける健康リスクを知らなかったこともあるが、「座りっぱなし」の「~っぱなし」という表現に引っかかったせいもある。「~っぱなし」は、辞書で調べると「その動作が持続しているさま、その動作をしたままで放置する意を表す。」とある。「~っぱなし」は「放す」という動詞が変化したものである。「蛇口から水が流れっぱなしになっている」「テレビをつけっぱなしで寝てしまった」等の文例が浮かび、比較的「あかんなあ」、という意味で私は「~っぱなし」を使っている。そのため「座りっぱなし」という言葉をマイナスイメージで受け取り「座って仕事をするのが悪かった?」と反発する気持ちもあり違和感を覚えたのだろう。一方で印象に残る表現でもある。「気をつけて」「注意して」の意味を込めて敢えて「~ぱなし」という表現を使っているのかもしれない。まだまだ暑い季節、エアコンは「つけっぱなし」でこまめに身体を動かそうと思う。
**************************************************
◇ 産業保健スタッフ研修会のご案内 ◇
『熱中症対策について(改正安衛則を含む)』
※6/23・7/29実施の研修と同じ内容です。
日時:令和7年8月8日(金) 14:00~16:00
会場:アーバネックス御池ビル東館 2階会議室
講師:京都産業保健総合支援センター 相談員 谷口 誠
『転倒災害防止対策はできていますか?~日常生活も含めた転倒災害防止対策~』
日時:令和7年8月26日(火) 14:00~16:00
会場:アーバネックス御池ビル東館 2階会議室
講師:関西労災病院 主任理学療法士 野間 健 氏
参加費:無料
お申込: https://www.kyotos.johas.go.jp/training#training02
※日医認定産業医の単位は付与されません。
**************************************************
◇ 第84回 全国産業安全衛生大会が大阪で開催されます!◇
例年の全国産業安全衛生大会より開催日時が前倒しになっています。
オンライン申し込みは、8月29日までです。
早めのお申込みでは…(当日申し込みとここが違う!)
1.8月下旬ごろから「パワーポイント集」の閲覧、ダウンロードができます。
すでに公表の分科会タイムテーブルと合わせて、参加したい分科会をあら
かじめ検討することができます。なお、過去に配布していた冊子(資料集)の
ご用意・配布はありません。
2.あらかじめ参加章をダウンロードしておくので入場がスムーズです。
同時開催の緑十字展(入場無料)にもぜひご参加ください。
参加申し込みは、以下のリンクから。
→ https://j-lppf2.jp/jisha-taikai2025/
**************************************************
◇ 両立支援コーディネーター基礎研修を受講された皆様へ ◇
メールアドレス、ご所属先など登録情報の変更がございましたら
以下のアドレス宛てにご連絡ください。
労働者健康安全機構勤労者医療課
両立支援コーディネーター養成研修事務局
E-mail: co-ryoritu@m.johas.go.jp
**************************************************
◇ 令和7年度 両立支援コーディネーター基礎研修 ◇
今年度の日程が公表されました。
第3回・第4回の募集期間
令和7年8月4日(月)13:00から8月15日(金)17:00まで
オンライン形式(動画配信研修+WEBライブ講習)での開催です。
応募者多数の場合は厳正なる抽選のもと、受講者を決定いたします。
≪詳細≫
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/2126/Default.aspx
**************************************************
◇メンタルヘルス対策支援サービスについて(無料)◇
促進員が事業場に赴き、お手伝いいたします。
・管理監督者教育への講師派遣
・若年労働者教育への講師派遣
・「こころの健康づくり計画」策定に関する支援
・「職場復帰支援プログラム」作成に関する支援
・ストレスチェック制度の導入や実施後の職場環境改善等に
関する支援
詳 細→ https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/mental
**************************************************
◇ 治療と仕事の両立支援サービスについて(無料)◇
当センターでは、治療を受けながら仕事を続けたい方、両立支援に取り組む事業場の方からの相談に応じています。
→ https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/ryoritsu
*出張相談窓口を開設しております。【要予約】
・京都大学医学部附属病院 毎月第3水曜日( 9:30~12:30)
・京都府立医科大学附属病院 毎月第2木曜日(10:00~12:00)
・京都市立病院 毎月第1金曜日(11:00~12:00)
・京都第二赤十字病院 随時
・京都第一赤十字病院 随時
・京都桂病院 随時
・京都医療センター 随時
・洛和会音羽病院 随時
・宇治徳洲会病院 随時
・京都山城総合医療センター 随時
・京都岡本記念病院 随時
・市立福知山市民病院 随時
・京都府立医科大学附属病院 北部医療センター 随時
**************************************************
◇健康保持増進のための職場訪問支援サービスついて(無料)◇
仕事中の「転倒災害」や「腰痛」等の労働災害に向けて、産業保健相談
員が事業場を訪問して健康測定・チエック、社内セミナーの実施や実技指
導、運動アドバイス等を行います。
健康で安心して働ける職場環境の形成を支援するという産業保健の観点
から、理学療法士の相談員による「運動指導等を通じた労働者の健康保持
増進のための支援」を実施することとなりました。ぜひご利用ください。
詳細→ https://www.kyotos.johas.go.jp/health-work-support-visit
**************************************************
◆京都産業保健総合支援センターご利用案内◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/about
◆相談のご案内◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/consultation
◆研修・セミナーのご案内◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/training-new
◆図書・教材のご案内◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/material
◆産業保健新着情報◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/archives/news
◆メールマガジン(バックナンバー)◆
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/mailmagazine/back-number
**************************************************
メールマガジンのお申込み・配信アドレスの変更、配信解除
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/mailmagazine
メールの内容・その他のお問合せ
https://www.kyotos.johas.go.jp/wp/inquiry
TEL: 075-212-2600 FAX: 075-212-2700
**************************************************
発 行 人 :松井 道宣 編 集 人 :田中 巧
編集協力 :産業保健相談員 メンタルヘルス対策・両立支援促進員
発行/配信:京都産業保健総合支援センター